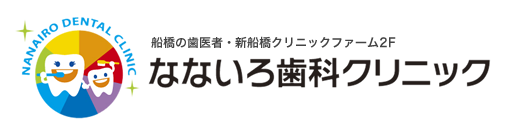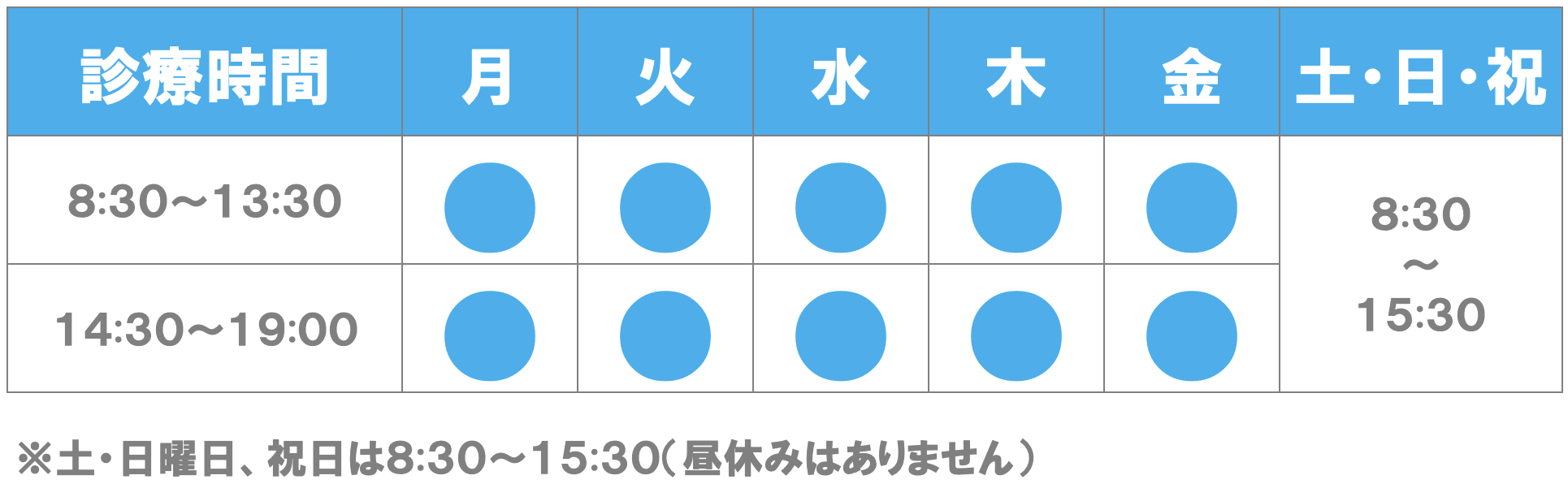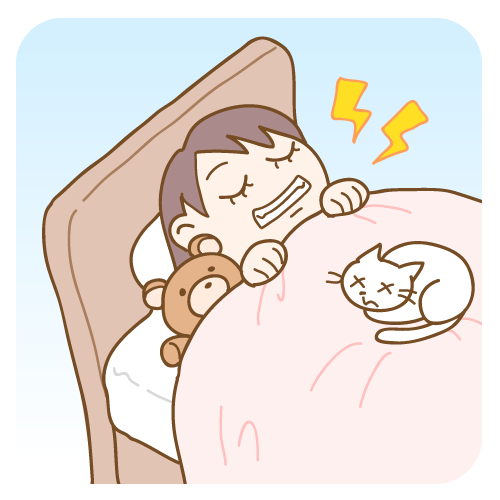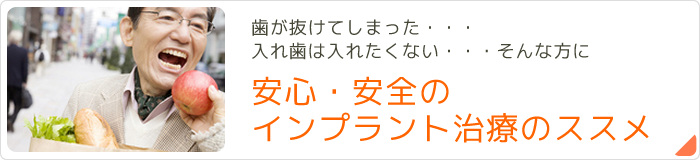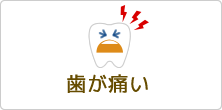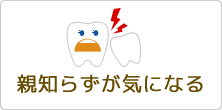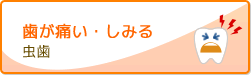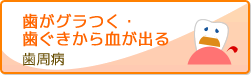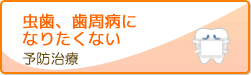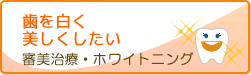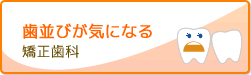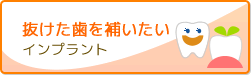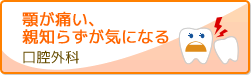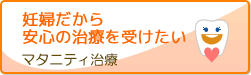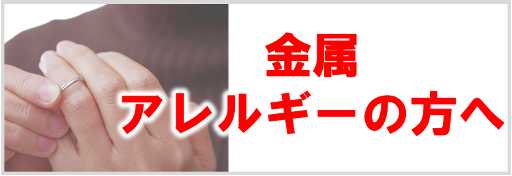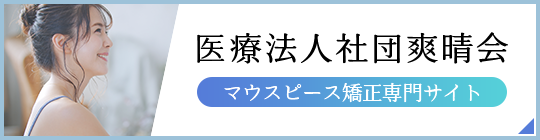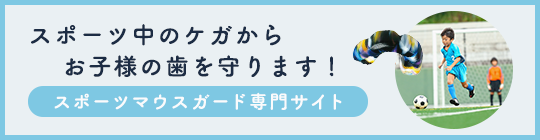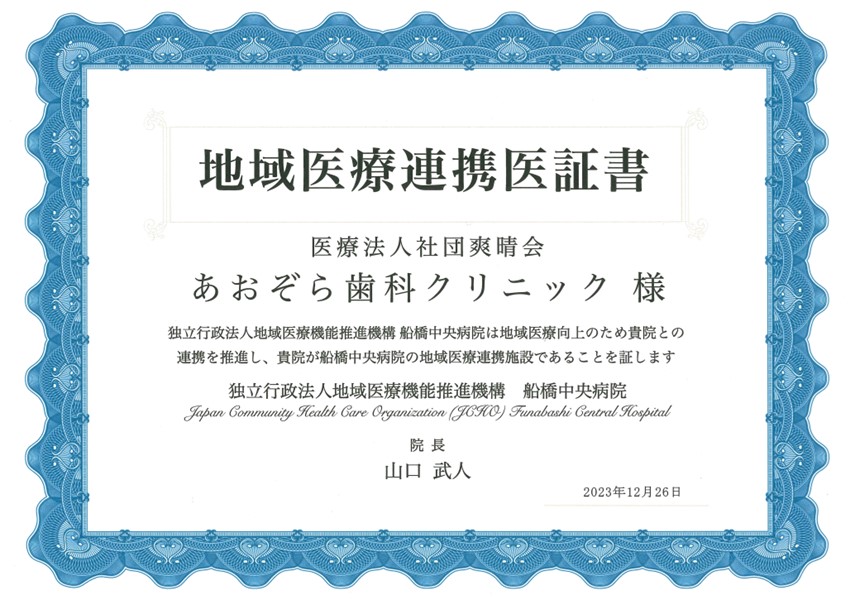子供の歯ぎしり、病気のサインかも?歯科で相談すべきタイミング
親子三代で安心して通える歯医者、船橋市のなないろ歯科クリニックです。
皆さん「子供の歯ぎしり」ってご存じでしょうか?眠っているときにギリギリと歯をこすり合わせる音がすることがありますが、成長の一過程で起こる場合もあれば、病気やかみ合わせの不調のサインである場合もあります。放置すると歯がすり減ったり、顎に負担がかかることもあるため注意が必要です。当院では患者様の状態を丁寧に確認し、必要に応じて予防や治療を行っています。この記事が皆様の参考になれば幸いです。
子供の歯ぎしりの原因と注意すべきサイン
子供が寝ているときに「ギリギリ」という歯ぎしりの音を立てると、保護者の方は驚いたり心配になることが少なくありません。乳歯から永久歯に生え変わる時期には一時的に見られることもありますが、場合によっては放置してはいけないサインを示していることもあります。ここでは、子供の歯ぎしりに関わる原因や注意が必要な症状について詳しく解説します。
乳歯から永久歯への移行による歯ぎしり
子供の歯ぎしりで最もよく見られるのが、歯の生え変わり時期に起こるものです。乳歯と永久歯が混在している時期は、上下の歯がうまくかみ合わず違和感が生じます。その違和感を解消するために、無意識のうちに歯をこすり合わせて調整しようとすることがあります。多くの場合は自然に落ち着くため、大きな心配はいりません。しかし歯ぎしりの頻度が高い場合や歯のすり減りが目立つ場合には、歯科でのチェックが必要となります。
ストレスや心理的な要因
子供は大人と同じように、環境の変化や人間関係の影響でストレスを感じることがあります。入園や入学、新しい習い事など、日常生活の中でプレッシャーを感じると、それが寝ているときの歯ぎしりとして現れることがあります。保護者からすると気づきにくい心理的負担が原因となっていることもあるため、生活環境や子供の気持ちを振り返ることも大切です。
睡眠の質や生活習慣との関係
浅い眠りや不規則な生活習慣が歯ぎしりの一因となることもあります。夜更かしや不規則な就寝時間は自律神経の働きを乱し、睡眠中に顎の筋肉が過度に動いてしまう場合があります。また、口呼吸が癖になっている子供は気道が不安定になりやすく、歯ぎしりが起こることも報告されています。
遺伝やかみ合わせの問題
家族に歯ぎしりの習慣がある場合、子供にも見られる傾向があります。さらに、噛み合わせに問題があると上下の歯が自然に合わず、その調整として歯ぎしりを繰り返すことがあります。こうしたケースでは歯の表面に過度な摩耗が起きやすく、長期間続くと顎関節や歯の神経に影響が出る場合もあります。
歯ぎしりによって起こり得るトラブル
子供の歯ぎしりをそのままにしておくと、次のようなトラブルが生じる可能性があります。
→歯の摩耗
強い力で歯をこすり合わせることで、歯の表面が削れやすくなります。乳歯は永久歯に比べてエナメル質が薄いため、短期間でもすり減りが進んでしまうことがあります。
→顎の負担
歯ぎしりは顎の関節や筋肉にも影響を与えます。朝起きたときに顎がだるい、痛みを訴えるといった症状が見られる場合は、顎関節への負担が大きくなっているサインです。
→歯列やかみ合わせへの影響
成長期に強い歯ぎしりが続くと、歯列や噛み合わせに歪みが生じる可能性があります。特に永久歯が生え揃う時期に歯ぎしりを繰り返すと、将来的な歯並びに影響することもあります。
注意すべきサインとは
子供の歯ぎしりは一時的なことが多いですが、以下のような症状が見られる場合には注意が必要です。
→歯の表面が削れて黄ばんで見える
→歯が欠けたり小さなヒビが入っている
→朝起きたときに顎や顔の筋肉が疲れている
→食事中に顎の痛みを訴える
これらの症状がある場合、ただの成長過程ではなく、治療や生活習慣の改善が必要なケースも考えられます。当院でも患者様の状態を確認し、必要に応じて適切な対応を提案しています。
家庭でできる観察ポイント
歯ぎしりが気になるときは、まずはご家庭でお子様の様子を観察することが大切です。寝ているときの音だけでなく、朝の状態や日中の行動にも注目してください。歯が削れていないか、顎の痛みを訴えていないか、日常生活に支障が出ていないかを確認することで、受診の必要性を判断しやすくなります。
歯ぎしりへの対処法と歯科受診の目安
子供の歯ぎしりは一時的なことも多く、すぐに治療が必要とは限りません。しかし、症状が続いたり歯や顎に悪影響が出ている場合には、適切な対応が必要となります。ここでは、家庭でできる工夫と歯科医院を受診すべき目安について詳しく解説します。
家庭でできる生活習慣の見直し
まずは毎日の生活の中でできる工夫から始めてみましょう。
→規則正しい睡眠習慣
十分な睡眠時間を確保し、毎日同じ時間に就寝・起床することで自律神経のバランスが整いやすくなります。睡眠が浅い状態は歯ぎしりを引き起こす一因となるため、睡眠の質を高めることが大切です。
→ストレスの軽減
子供は大人以上に環境の変化に敏感です。学校や習い事、人間関係などで不安を感じていないかを見守り、安心できる時間を増やしてあげることが重要です。寝る前に親子でゆったりと会話をする、好きな絵本を読むといった習慣は、心の安定につながり歯ぎしりの緩和にも役立ちます。
→食生活の工夫
硬いものばかりを噛みすぎると顎に負担がかかる場合があります。一方で、噛む機会が少なすぎても顎の発達に影響するため、バランスの良い食事を心がけることが大切です。
→口呼吸の改善
口呼吸が習慣化していると気道が不安定になり、歯ぎしりの原因になることがあります。鼻呼吸を意識させたり、耳鼻科での相談を検討することも有効です。
マウスピースの使用について
歯ぎしりによる歯の摩耗や顎の負担が強い場合には、歯科医院でマウスピースを作成することがあります。特に永久歯に移行している時期の子供にとっては、歯の健康を守るための有効な方法となります。マウスピースは就寝時に装着することで歯と顎へのダメージを和らげる役割を果たします。当院でも、患者様の年齢や歯の状態に合わせて適切なものを提案することが可能です。
ただし、すべての子供に必要というわけではありません。成長に伴って自然に歯ぎしりが減少する場合も多いため、使用の判断は専門的な診察を受けた上で行うことが望まれます。
歯科受診を検討すべき症状
歯ぎしりが見られる場合でも、受診が必要なケースと様子を見てもよいケースがあります。次のような症状がある場合には歯科医院でのチェックをおすすめします。
→歯がすり減って形が変わってきている
→歯の一部が欠けたり、ヒビが入っている
→朝起きたときに顎が痛い、または疲れている
→食事の際に顎の違和感や痛みを訴える
→長期間にわたり歯ぎしりの音が続いている
こうした症状は単なる成長過程ではなく、歯や顎に実際のダメージが及んでいるサインである可能性が高いです。放置すると歯並びや噛み合わせに悪影響が出ることもあるため、早めの対応が安心につながります。
歯科での診察内容
歯科医院では、歯ぎしりによる歯の摩耗や顎関節の状態をチェックします。必要に応じてレントゲン撮影を行い、歯や顎の骨に異常がないか確認します。また、噛み合わせのバランスを確認し、将来的に影響が出そうな場合には治療や経過観察を提案することもあります。
当院でも、患者様一人ひとりに合わせた診察を行い、生活習慣の改善やマウスピースの装着などを通じて歯の健康を守るためのサポートをしています。
成長とともに変化する歯ぎしり
子供の歯ぎしりは年齢によって原因や影響が異なります。乳歯期の歯ぎしりは一時的な調整行動であることが多いですが、永久歯に変わるタイミングや思春期以降に続く場合は注意が必要です。顎の成長や歯列の形成に大きな影響を及ぼす可能性があるため、保護者が気づいたときに適切に対応してあげることが重要です。
家族でできるサポート
子供の歯ぎしりを改善するためには、家庭内でのサポートも欠かせません。寝る前のリラックスタイムを作る、安心できる環境を整える、ストレスの原因を取り除いてあげるといった取り組みは歯ぎしりの軽減につながります。また、定期的に歯科医院でチェックを受けることで早期発見・早期対応が可能になります。
今回は子供の歯ぎしりについて説明しました。歯の生え変わりや心理的な要因、生活習慣などが原因となることが多く、一時的な場合もありますが、歯の摩耗や顎の不調につながることもあります。家庭での観察や生活習慣の見直しは大切ですが、歯の欠けや顎の痛み、長期間続く歯ぎしりは注意が必要です。なないろ歯科クリニックでは、患者様一人ひとりの症状に合わせたご相談を随時実施しておりますので、ぜひご相談ください。
本記事はなないろ歯科クリニック院長、北條將貴監修のもと作成しています。

お知らせ
-
2026.01.04
-
2025.12.02
-
2025.09.01
-
2025.08.07
-
2024.12.01
-
2024.10.18
-
2024.08.05
-
2024.05.24
-
2024.05.07
-
2023.12.15